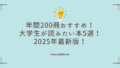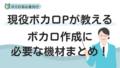こんにちは!
本日もブログをご覧いただきまして、ありがとうございます!!
今回は、ボカロ文化の進化を代表曲とともに振り返り、現在メジャーデビューしたアーティストや最新楽曲も紹介する記事になります!

ボカロが大好きな曲や、現在メジャーデビューしているアーティストが実はボカロ出身のアーティストということを知りたい方に特におすすめの記事になります!!

簡単に自己紹介です。
- ボカロP
- 薬大生
- ブログ
Youtubeやストリーミングでボカロあげてるので聴いてくれると嬉しいです!!
・Youtube
・ストリーミング配信(Spotify、Apple Music etc..)

・Linktree

目次
1. ボカロ文化の黎明期(2007~2010年)
背景
2007年、クリプトン・フューチャー・メディアから発売された「初音ミク」は、音声合成技術を活用したバーチャルシンガーとして登場しました。この革新的な技術は、音楽制作のハードルを大幅に下げ、個人クリエイターが自由に楽曲を発表できる新しい時代を切り開きました。特にニコニコ動画を中心に、ボカロ楽曲が急速に広がり、コミュニティが形成されました。

当時の音楽は特定の才能に恵まれた、一部の人にしか釣れないものという認識だったので衝撃的でした!!
代表曲
- みくみくにしてあげる♪(ika)

初音ミクの名を一躍有名にした楽曲で、ボカロ文化の象徴的な存在となりました。ニコニコ動画での再生数が爆発的に伸び、「VOCALOID伝説入り」の最初の楽曲として記録されています。
- メルト(ryo/supercell)

ボカロ楽曲の可能性を広げた一曲です。甘酸っぱい恋愛をテーマにした歌詞とメロディが多くのリスナーの心を掴み、「メルトショック」と呼ばれる社会現象を引き起こしました。
文化的意義
- 初音ミクが登場し、DTM愛好者による作品がニコニコ動画で大きなムーブメントを生んだ。
- 個人クリエイターの台頭: プロではない個人が、音楽制作や動画投稿を通じて多くの人々に影響を与えることが可能になりました。
- 二次創作の活性化: 楽曲を元にしたイラスト、アニメーション、踊ってみた動画など、多様な二次創作が生まれ、コミュニティがさらに拡大しました。
- 音楽の民主化: 音楽制作が特定のプロフェッショナルだけのものではなくなり、誰もが参加できる文化として進化しました。
- 当時のトレンド
- ニコニコ動画の影響力: ボカロ楽曲の多くがニコニコ動画で公開され、ランキング上位に入ることで注目を集めました。
- 初音ミクのキャラクター性: 単なる音声合成ソフトではなく、キャラクターとしての魅力がファンを惹きつけました。

ボカロ文化が始まった原風景になります!アツい!!笑
2. ボカロ文化の多様化と進化(2011~2015年)
背景
この時期、ボカロ文化はジャンルの幅を広げ、より多様な音楽スタイルが生まれました。VOCAROCK、エレクトロニカ、ポップスなど、従来の枠を超えた楽曲が登場し、ボカロPたちは独自の音楽性を追求しました。また、楽曲のストーリー性や世界観が重視されるようになり、リスナーとの深い共感を生む作品が増加しました。
代表曲
- 千本桜(黒うさP)

ボカロ曲といえば、自分はこの曲がはじめに浮かびます!!アチいのよ!!笑
また和楽器バンドさんのカバーも大好きです!
- カゲロウデイズ(じん)
文化的意義
- ジャンルの拡張: ボカロ楽曲が多様化し、より幅広いリスナー層に受け入れられるようになりました。
- ストーリー性の重視: 楽曲が単なる音楽としてだけでなく、物語を伝える手段として進化しました。
- メディアミックス展開: 楽曲が小説、アニメ、舞台などに展開され、ボカロ文化がより広範囲に影響を与えるようになりました。
当時のトレンド
- ニコニコ動画のランキング: 楽曲がランキング上位に入ることで注目を集め、ボカロPの知名度が向上しました。
- ライブイベントの増加: ボカロキャラクターを使用したライブイベントが開催され、ファンとの直接的な交流が可能になりました。
3. ボカロ文化のグローバル展開(2016~2020年)
背景
この時期、初音ミクをはじめとするボカロキャラクターが海外でのライブイベントやコンサートを通じて注目を集めました。特に、北米、ヨーロッパ、アジア各地での公演が成功を収め、ボカロ文化が「クールジャパン」の一環として認識されるようになりました。また、VOCALOIDソフトウェア自体も進化し、多言語対応やリアルな歌声の表現が可能になり、海外のクリエイターやリスナーにも受け入れられるようになりました。
代表曲
- 砂の惑星(ハチ)
- ワールズエンド・ダンスホール(wowaka)
アーティストについて

ハチとwowakaはボカロ界の双璧のイメージですよね!!
もう知っている方も多いと思いますが、ハチは米津玄師のボカロP時代の名前になります!!
日本を代表するアーティストがボカロ出身ということだけで、ご飯3倍はいけちゃいますね。笑
- 米津玄師(ハチ) ボカロP時代の代表曲:「パンダヒーロー」 メジャー後の代表曲:「Lemon」
文化的意義
- 国際的な認知度の向上: ボカロキャラクターが海外の音楽イベントやアニメコンベンションで紹介され、国際的な認知度が大幅に向上しました。
- 多文化交流の促進: ボカロ楽曲が多言語で制作されるようになり、異なる文化圏のファン同士の交流が活発化しました。
- クリエイターの多様化: 海外のクリエイターがボカロソフトを活用し、独自の楽曲を制作することで、ボカロ文化がさらに多様化しました。
当時のトレンド
- ライブイベントの拡大: 初音ミクを中心としたライブイベントが、音楽の新しい形として注目されました。
- SNSと動画プラットフォームの活用: YouTubeやTwitterを通じて、ボカロ楽曲が世界中に拡散されました。
4. 現在までの潮流(2021~)
背景
2021年以降、ボカロ文化は再びブームを迎えています。特に、TikTokやYouTubeなどのSNSを通じて、若い世代にボカロ楽曲が広がり、新たなファン層を獲得しました。また、AI技術を活用した音声合成ソフトウェアの進化により、よりリアルで多様な歌声が可能になり、クリエイターの表現の幅が広がっています。
代表曲
- ヴァンパイア(DECO*27)
- フォニイ(ツミキ)
メジャーデビューしたアーティスト
- YOASOBI(Ayase) ボカロP時代の代表曲:「幽霊東京」 メジャー後の代表曲:「アイドル」
代表的な出来事
- 新世代ボカロPの台頭 syudouやKanaria、ツミキなどの新世代ボカロPが登場し、彼らの楽曲がSNSでバイラルヒットを記録しています。特に「グッバイ宣言」(chinozo)や「フォニイ」(ツミキ)は、若い世代に支持される代表的な楽曲です。
- AI音声合成技術の進化 CeVIO AIやNEUTRINOなどの新しい音声合成ソフトウェアが登場し、従来のVOCALOIDを超えるリアルな歌声が実現されています。これにより、ボカロ楽曲のクオリティがさらに向上しました。
syudou

syudouさんはAdoさんの『うっせえわ』を作った人です!!
chinozo
サツキ
原口沙輔
文化的意義
- 新たなファン層の獲得: TikTokやYouTubeを通じて、ボカロ文化が若い世代に広がり、再び注目を集めています。
- クリエイターの多様化: 新しい音声合成ソフトウェアの登場により、より多様なクリエイターがボカロ楽曲制作に参加しています。
- 二次創作の活性化: ボカロ楽曲を元にした「歌ってみた」や「踊ってみた」動画がSNSで人気を博し、二次創作文化がさらに広がっています。
メジャーデビューしたボカロP出身アーティスト

その他のボカロ出身の、メジャーアーティストもまとめてみました!!
- YOASOBI(Ayase)
- ボカロP時代の代表曲:「ラストリゾート」「幽霊東京」
- メジャーデビュー後の代表曲:「夜に駆ける」「アイドル」
ヨルシカ(n-buna)
- ボカロP時代の代表曲:「透明エレジー」
- メジャーデビュー後の代表曲:「ただ君に晴れ」「花に亡霊」
- 須田景凪(バルーン)
- ボカロP時代の代表曲:「シャルル」
- メジャーデビュー後の代表曲:「パレイドリア」「veil」
- Eve
- ボカロP時代の活動を経て、現在はシンガーソングライターとして活躍。
- メジャーデビュー後の代表曲:「廻廻奇譚」「ドラマツルギー」
プレイリスト

ということで、本当に名曲だらけのボカロ文化ですが、Spotifyでプレイリストを作ったのでぜひ聴いてください!!
今回取り上げることができなかったボカロPさんの曲もいっぱい入ってます!
プレイリストを保存してヘビロテしまくってください!笑
まとめ
ボカロ文化は2007年の「初音ミク」登場から始まり、黎明期、多様化、グローバル展開、そして現代に至るまで進化を続けています!
これからも新しいクリエイターや技術との融合により、さらなる成長が期待されます!!
皆さんでこれからもボカロを盛り上げていきましょう!!

私の曲もよかったら聴いてね!!笑
・ストリーミング配信(Spotify、Apple Music etc..)

それでは最後まで読んでいただきまして、ありがとうございました!!
SNSリンク集
Linktree

インスタ

X,Twitter
TikTok
Threads
ストリーミング配信(Spotify、Apple Music etc..)

YouTube
YouTubeサブ
ニコニコ動画

PeDeの日常ブログ

Podcast PeDeのオールナイトキャスト

ホームページ
PeDe portfolio
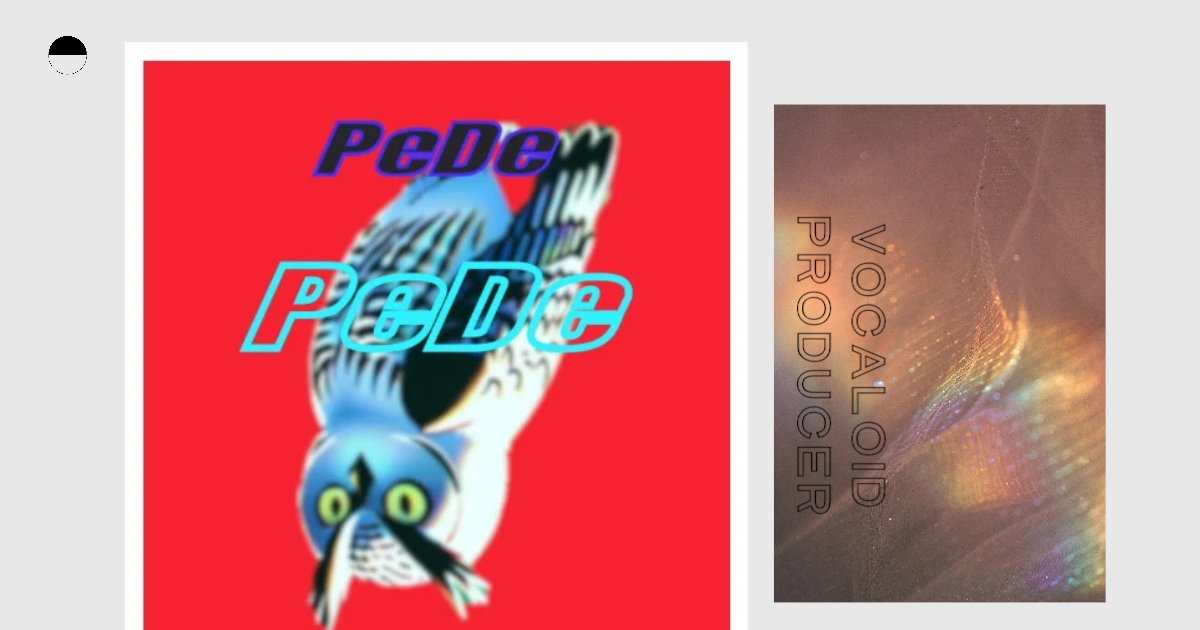
note
PeDe|note